立教大学総合型選抜の全体像と対策|面接・書類作成・小論文の攻略法
- 株式会社EQAO教育グループ

- 2024年10月28日
- 読了時間: 14分
更新日:3月6日

▶︎1. 立教大学の総合型選抜(自由選抜入試)とは?

1.1 総合型選抜の目的と立教大学での位置づけ
立教大学の総合型選抜(自由選抜入試)は、学力だけに頼らず、受験生の多様な背景や実績、個性を総合的に評価することを目的とした入試制度です。
従来の一般入試とは異なり、総合型選抜では書類審査や小論文、面接などを通じて受験生の持つ「非認知能力」や「主体的な学習態度」を見極めることが重視されます。このため、学内外の活動やプロジェクトへの取り組みを通じて培ったスキルや自己表現力が選抜において重要な要素となります。
立教大学の総合型選抜は、入試改革の一環として「多様な価値観と社会性を持った人材の育成」を掲げ、特にリーダーシップやコミュニケーション能力、課題解決力など、大学生活での成長に不可欠な資質を持つ学生の受け入れに力を入れています。
選考を通じて、「他者貢献」の精神を実践できる人材を発掘することが立教大学の特徴であり、この点が他の大学の総合型選抜と一線を画するポイントとなっています。
1.2 総合型選抜の選考フローと評価基準
立教大学の総合型選抜は、通常、一次選考での書類審査と二次選考での小論文・面接を組み合わせたプロセスを経て、受験生の多様な能力を評価します。この選考フローの各段階で異なる評価基準が設定されており、受験生の「自己表現力」と「思考力」、および「対人コミュニケーション能力」が総合的に判断されます。
一次選考:書類審査
一次選考の書類審査では、志望理由書、活動報告書、調査書などが提出され、受験生の高校での学習成果や課外活動が重要視されます。志望理由書では「立教大学での学びの目的」や「社会で実現したい目標」についての具体性が求められ、受験生の将来のビジョンが評価対象になります。
二次選考:小論文・面接
二次選考の小論文では、与えられたテーマに対する論理的な意見表明が必要です。面接では「受験生が大学生活を通じて何を学び、どのような人物になりたいか」が重視されるため、志望動機の明確さとコミュニケーション力が重要視されます。
1.3 学部別の特徴と選抜倍率の傾向
立教大学の総合型選抜(AO入試)は、学部ごとに異なる選抜基準と倍率が設定されており、学部の特徴に合わせた入試内容が評価ポイントとして設けられている点が特徴です。
たとえば、異文化コミュニケーション学部では、高度な英語力や異文化理解に対する意識が重視され、英語資格のスコア提出や、異文化に関する具体的な経験が求められることが多いです。法学部や社会学部などでは、論理的思考や社会問題への理解が評価基準に含まれることがあり、それぞれ異なる評価内容が設定されています。
選抜倍率の傾向
学部別の選抜倍率は年によって異なりますが、異文化コミュニケーション学部や社会学部などの人気学部では、10倍前後の高倍率になることもあります。
これは、総合型選抜を通じて個性豊かな人材を集めたいという大学側の意図と受験生からの高い志望度が反映されているためです。倍率は毎年変動するため、受験生は事前に最新の倍率情報を確認し、適切な準備を進めることが重要です。
▶︎2. 学部別・立教大学総合型選抜の対策方法

2.1 社会学部・法学部の総合型選抜対策
立教大学の社会学部と法学部の総合型選抜では、社会的な関心と論理的な思考力を兼ね備えた人材が求められます。
社会学部では、特に「多文化理解」や「現代社会に対する分析力」が評価される傾向があり、選考ではエッセイやディスカッションでの柔軟な意見表現が重要視されます。社会学部においては、自らの考えを深めるための読書や課外活動の記録がアピールポイントとして有効です。
一方、法学部では、法律やビジネス関連の基礎知識とともに、論理的な問題解決力を問われるケースが多く、選抜過程では書類審査や小論文での実力が評価対象です。
書類作成では、「法的な視点から見た社会課題」に対する自分の考えを明確に伝えることが重要で、面接ではその論理性や一貫性が確認されるため、日頃からニュースや社会問題に関心を持ち、議論する習慣が役立ちます。
2.2 異文化コミュニケーション学部の選考ポイント
立教大学の異文化コミュニケーション学部では、高い語学力と多様な文化背景に対する理解力が求められるため、英語の資格スコア(英検やTOEFLなど)や異文化に関する実体験が評価対象となります。
この学部では、書類審査と面接に加え、論述力を確認するための小論文が実施されることが多く、与えられたテーマに対して異文化の視点からの独自の考察が求められます。
小論文では「異文化理解や社会貢献」に関するテーマが出題されることが多いため、具体的な異文化体験や、その中で得た学びを明確に表現する練習が有効です。
また、面接では「自分の文化的背景と他者の文化への理解」を問われるため、過去の体験をどのように自分の価値観に結びつけたかを言語化することが重要です。以上の点を踏まえて、総合型選抜の特性に応じた対策を行うことが合格への道につながります。
2.3 経済学部・経営学部の出願基準と対策
立教大学の経済学部と経営学部の総合型選抜では、経済・経営分野への強い関心や社会的視点が重視されます。
経済学部では、経済学への知識だけでなく、データに基づく分析力や思考力も求められるため、選考では小論文や面接での論理的な意見表現が重視されます。経済ニュースを継続的に追い、時事問題についての自分の意見をまとめておくことが対策として有効です。
経営学部の総合型選抜では、ビジネスに対する熱意やリーダーシップの経験が評価されることが多く、書類審査では志望理由書に「経営学を通じて何を実現したいか」という明確な目標が求められます。また、面接では「具体的なリーダーシップ経験」や「社会に与える影響力」が問われるため、過去のエピソードを振り返り、明確に伝えられる準備が必要です。
▶︎3. 志望理由書と活動報告書作成のコツ

3.1 志望理由書のテーマ設定と構成
立教大学の総合型選抜では、志望理由書が合否を左右する重要な書類です。志望理由書は、「立教大学で何を学び、将来どのように活かしたいか」を具体的に伝える場であり、学部での学びが自分の目標にどうつながるのかを論理的に説明する必要があります。
例えば、社会学部志望者であれば「現代社会の課題に対する問題意識とそれを解決するための具体的な学び」について書くと説得力が増します。
また、総合型選抜を通じて上智大学・立教大学・青山学院大学に合格した受験生の体験動画には、志望理由書作成や面接対策で意識すべきポイントが詳しく紹介されています。
こうした実際の体験を参考にすることで、志望理由書や活動報告書における自己表現のコツが学べます。具体的なエピソードを通して自分の強みや将来の目標をアピールする方法を確認しておきましょう。
参考動画:
3.2 活動報告書で評価される具体例と自己PR方法
立教大学の総合型選抜において、活動報告書は自分の過去の取り組みや成長を伝えるための重要な書類です。活動報告書では「主体的な活動」と「成果」を具体的に示すことで、受験生の個性や行動力が評価対象となります。
例えば、部活動やボランティア、リーダーシップを発揮したプロジェクトなどの具体的な経験を記載し、そこで学んだことや達成したことを明確に伝えることが大切です。
自己PRでは、単なる事実の羅列に終わらないよう、活動を通じて得た成長や将来への意欲につなげる表現が重要です。例えば、「プロジェクトに取り組む中でどのような役割を担い、どのような課題に対処したか」を示し、得られたスキルが今後の学びや目標にどうつながるかを伝えましょう。
また、「立教大学の学びをどのように活かしたいか」を明確にすることで、志望動機にも一貫性が生まれます。
3.3 立教大学で求められる自己PRの要素
立教大学の総合型選抜では、自己PRにおいて「自分の独自性や強み」を明確にアピールすることが重要です。志望学部の学びと結びつけて、自分の経験やスキルがどのように役立つかを具体的に示すことで、自己PRがより効果的になります。
例えば、社会学部志望者は、社会問題への関心やリーダーシップ経験が、自分の学びや将来のビジョンにどう繋がるかを述べるとよいでしょう。
自己PRの際には、立教大学が掲げる「他者貢献」や「グローバルな視野」を意識し、過去の活動やプロジェクトから得た教訓をもとに自分の成長や学びを伝えます。また、今後の学習意欲や大学での挑戦意欲も示すことで、志望理由書や活動報告書と内容に一貫性が生まれ、より説得力が増します。
▶︎4. 書類審査と小論文対策のポイント
4.1 調査書の記載方法と推薦状の活用法
立教大学の総合型選抜では、調査書と推薦状も重要な評価要素として扱われます。調査書には、学業成績だけでなく、受験生の人柄や課外活動の実績などが含まれるため、バランスの取れた人材であることが伝わるような内容が求められます。成績評価に加えて、特に努力した科目や得意分野が明確に示されていると、アピールポイントとなります。
推薦状においては、志望する学部や学科に関連する実績や経験を具体的に記載してもらうことが望ましいです。例えば、法学部志望であれば、倫理的判断力や責任感をアピールする具体的なエピソードが評価される要素として有効です。
推薦状は、自分がどのような資質を持ち、立教大学での学びにどう貢献できるかを客観的に示す手段となるため、作成を依頼する際に自分の意図を伝えておくことも重要です。
4.2 小論文で評価される論理展開と過去の出題分析
立教大学の総合型選抜において、小論文は受験生の論理的思考力と表現力を見極める重要な試験です。小論文では、課題に対する深い理解と論理的な意見形成が求められ、テーマに関連する背景知識や具体的な事例を織り交ぜて書くことが高評価につながります。
例えば、社会問題や異文化理解といったテーマでは、関連ニュースや自分の体験に基づく視点を活用すると説得力が増します。
過去の小論文の出題内容を分析すると、特に「課題解決に対する独自の意見」や「立教大学の理念と合致する考え方」を含めることが重要とされています。
たとえば、異文化コミュニケーション学部では異文化理解に基づく社会貢献について問われるケースがあり、社会学部では現代社会における課題を意識した論述が求められます。小論文の準備として、関連分野の知識を深め、複数の視点から論じる練習を重ねることが成功への近道です。
4.3 小論文練習に効果的なトレーニング法
立教大学の総合型選抜の小論文で高評価を得るためには、論理的な構成や主張の一貫性を重視したトレーニングが重要です。小論文の練習では、「序論・本論・結論」の構成を意識し、簡潔で明確な表現を心がけることが効果的です。
また、毎回異なるテーマに沿って複数の立場から考察を加え、多角的に物事を捉える練習をすることで、実際の試験でも柔軟に対応できる力が養われます。
さらに、頻出テーマに関連する基礎知識を習得し、それをもとに具体例を交えた文章を組み立てる練習も有効です。
例えば、異文化理解や社会貢献に関するテーマに備えて、自分の経験や身近な社会問題を例に挙げて論述することで、読者に伝わりやすい内容を作り上げることができます。時間を計っての模擬試験形式の練習も、時間配分のスキル向上に役立つためおすすめです。
▶︎5. 面接・ディスカッションの準備方法
5.1 面接での自己アピールと志望動機の伝え方
立教大学の総合型選抜の面接では、「自分の強みや志望動機を具体的かつ論理的に伝える力」が重視されます。面接官は、受験生が大学での学びに対してどれだけ明確なビジョンを持っているかを見極めるため、自己アピールと志望理由が一貫していることが評価のポイントとなります。
具体的には、「なぜ立教大学を選んだのか」「将来どのように学びを活かしたいのか」を明確に述べ、大学生活での目標や取り組みたい活動を含めた意欲を示すことが効果的です。
自己アピールでは、自分の経験や特技が立教大学の学びにどう役立つかを伝えることが重要です。たとえば、リーダーシップや課題解決能力など、具体的なエピソードをもとに自分の強みを伝えることで、説得力が増します。緊張を抑えてリラックスし、自分の言葉で自然に表現することも大切なポイントです。
5.2 グループディスカッションのコツと対策
立教大学の総合型選抜で行われるグループディスカッションは、受験生の協調性や論理的なコミュニケーション能力を評価する重要な場です。ディスカッションでは、与えられたテーマについて他の受験生と意見を交換しながら、積極的かつ柔軟に発言することが求められます。
単に意見を主張するだけでなく、他者の意見を傾聴し、適切なタイミングで自分の考えを述べることで、グループとしてのまとまりが生まれ、評価につながります。
対策として、普段からさまざまなテーマについてディスカッションを行い、要点をまとめる練習を重ねるとよいでしょう。また、他のメンバーが意見を述べやすいように質問を投げかけたり、議論を整理して進行役を担うなどの役割分担を意識した練習も効果的です。
グループディスカッションでは、個々の意見だけでなく、全体の協調性とテーマに対する総合的な理解が評価されるため、バランスの取れた参加が鍵となります。
5.3 本番を想定した面接練習の重要性
立教大学の総合型選抜の面接で高評価を得るには、本番さながらの面接練習を繰り返すことが極めて重要です。模擬面接を通じて、自己紹介や志望理由、活動報告に関する質問に対する回答を練り上げ、どのような質問にも対応できる柔軟な応答力を身につけることが求められます。
面接官からの質問には、自分の意見を的確に伝え、具体例を交えて回答することで、より説得力のある受け答えが可能となります。
本番に備えた対策として、面接練習ではフィードバックを受けながら改善点を確認し、自信を持って表現できるようにすることも大切です。表情や姿勢、言葉遣いなど、全体の印象が評価につながるため、動画撮影などで自分の話し方や表情を確認する方法も効果的です。
また、想定外の質問にも対応できるように準備し、「志望動機」「学びたい内容」「将来の目標」など基本的な質問への回答をスムーズにできるようにすることで、面接での印象が大きく向上します。
▶︎6. 立教大学総合型選抜に向けた準備と対策まとめ
6.1 長期・短期の学習計画の立て方
立教大学の総合型選抜で成功するためには、長期的な目標と短期的な対策の両方を計画的に進めることが大切です。
長期計画では、志望学部に必要な知識の習得や関連分野の理解を深めるための学習スケジュールを作成し、主要な書類(志望理由書や活動報告書)の準備を早めに開始します。また、特定のスキル(英語力や論理的思考など)を必要とする学部の場合、計画的に学力を高めるための時間も確保することが重要です。
短期的な対策としては、面接や小論文の練習を本番に近い形で繰り返し行い、入試の直前には自己分析や志望理由を再確認することで、表現の一貫性と説得力を高めます。また、模擬試験や面接練習などで時間管理や予測される質問への応答力を高めることで、実際の試験でのパフォーマンスを向上させることができます。
6.2 効率的な勉強法とモチベーション維持のポイント
総合型選抜に向けた準備期間が長期にわたるため、効率的な勉強方法とモチベーション維持が合格に向けた重要な要素です。具体的には、自分のペースに合わせて勉強量を調整し、定期的に目標を振り返ることで集中力を維持します。
また、志望学部の関連分野に興味を持ち続けるために、学外のセミナーやワークショップに参加するなど、学びを深める機会を積極的に取り入れることもおすすめです。
また、日々の進捗を確認できるチェックリストや勉強の記録を残すことで、達成感を感じながら学習を続けることができます。長期目標が達成されることで自己成長を実感でき、入試に向けた自信にもつながります。特に、目標を細かく設定し、段階的に達成することでモチベーションが維持しやすくなります。
6.3 成功に向けた最終確認と当日の心得
立教大学の総合型選抜本番では、準備してきたことを最大限に発揮するための心構えが重要です。最終確認としては、志望理由書や小論文、活動報告書の内容が一貫しているかを見直し、面接で話す内容とズレがないようにします。また、当日に備えて面接やディスカッションの練習を積んでおくことで、緊張してもスムーズに対応できる準備が整います。
試験当日には、リラックスしながら自信を持って自分の言葉で表現することを心がけましょう。緊張が高まる中でも、自分が立教大学で成し遂げたいことに集中し、入試全体を通じてブレない姿勢を示すことで、面接官に対して良い印象を与えることができます。事前準備を信じて挑む姿勢が、成功への大きな鍵となるでしょう。
▶︎立教大学総合型選抜対策はEQAOで徹底サポート!
立教大学の総合型選抜合格を目指す方へ、志望理由書から面接までを網羅した対策サポートをご提供します。EQAOでは、大学入学後も役立つ思考力やコミュニケーション力の向上を重視し、あなたの強みを最大限に引き出します。専門家の指導のもと、自分らしく効果的にアピールできる対策を進めましょう。
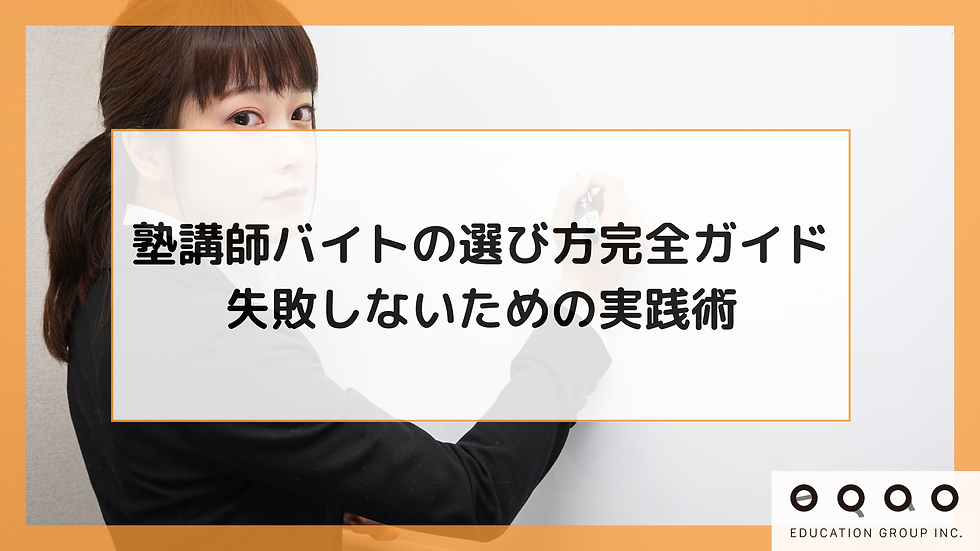


コメント