総合型選抜は併願できる?可能な大学や効果的な対策方法とは?
- 株式会社EQAO教育グループ

- 3月24日
- 読了時間: 18分
更新日:3月25日

▶︎1. 総合型選抜とは

1.1 総合型選抜の概要
みなさんは「総合型選抜」という入試方式をご存じですか?これは、学力試験の点数だけではなく、受験生の個性や意欲を重視する入試制度のことです。以前は「AO入試」と呼ばれていましたが、現在は「総合型選抜」という名称に変わっています。
総合型選抜とは?
総合型選抜は、従来の一般入試とは異なり、次のような特徴があります。
学力試験だけでなく、多面的・総合的に評価される
→ 高校での活動実績や、志望理由書、面接、小論文などを総合的に評価されます。
志望校への強い熱意が求められる
→ 「なぜこの大学・学部を志望するのか?」をしっかり伝えることが重要です。
出願時期が早く、秋には合格が決まることも
→ 早い大学では6月〜7月にエントリーが始まり、10月〜12月には合否が決まります。
つまり、一般入試と比べて「学力試験の点数に自信がないけれど、大学で学びたいことが明確な人」に向いている入試方式なんです。
どんな人に向いているの?
総合型選抜は、以下のような人におすすめです。
・学校の成績(評定)があまり高くないが、得意分野がある人
・将来の目標が明確で、その分野についての活動実績がある人
・面接やプレゼンテーションが得意な人
・早めに受験を終えて、大学入学前にやりたいことがある人
たとえば、「高校時代にボランティア活動を続けてきた」「プログラミングでアプリを開発した」といった具体的な経験があると、有利になりますよ!
1.2 総合型選抜の特徴とメリット
総合型選抜は、一般入試とは異なる評価基準があり、多くのメリットがあります。どのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
学力試験だけではなく、多面的な評価が行われる
総合型選抜では、一般入試のような学力試験の点数だけでなく、次のようなポイントも評価されます。
志望理由書や自己推薦書:志望動機や将来の目標が明確であることが重要。
面接・プレゼンテーション:自分の考えを論理的に伝える力が求められる。
活動実績:部活動やボランティア、コンテスト受賞歴などが強みになる。
つまり、「試験の点数だけでは測れない、個々の強みや個性を活かせる入試方式」ということなんです。
早い時期に合格が決まり、余裕を持てる
一般入試は1〜2月に試験を受け、合格発表は2〜3月になることが多いですが、総合型選抜では10〜12月ごろに合格が決まることがほとんどです。
・ 合格後は、一般入試の勉強から解放される
・ 大学入学前に語学留学やスキル習得の準備ができる
・ 進学先が早く決まり、精神的な負担が軽減される
特に、将来やりたいことが明確な人にとって、早めに進学が決まるのは大きなメリットになりますよ!
志望校に合格しやすいチャンスがある
一般入試は倍率が高く、競争率10倍以上の大学もあります。しかし、総合型選抜は、大学側が「ぜひこの学生に入学してほしい」と思う人材を探す方式なので、しっかり対策をすれば合格率を上げることができます。
▶︎2. 総合型選抜における併願の基本知識

2.1 併願とは何か?
受験生の中には、「併願」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?併願とは、複数の大学や学部を同時に受験することを指します。
一般入試ではよく見られる方法ですが、総合型選抜でも併願が可能な場合があります。併願を上手に活用すれば、受験のチャンスを広げることができるんです。
併願の基本的な考え方
併願を行うことで、受験する大学が増えるため、合格のチャンスが広がります。しかし、併願を行う際には、次のような点に注意する必要があります。
試験日程が重なると受けられない
大学ごとに試験日程が異なるため、試験日程をしっかり確認し、重ならないようにスケジュールを調整しましょう。
入試方式や評価基準の違いを理解する
総合型選抜と一般入試では評価の基準が異なります。それぞれの試験に対する準備をしっかり行うことが大切です。
併願のメリット
併願の最大のメリットは、受験する大学の選択肢を広げることです。複数の大学を受けることで、合格のチャンスを増やし、万が一第一志望に落ちても、他の大学で合格する可能性が残ります。
また、併願をすることで、受験に対する不安やプレッシャーが軽減される場合もあります。
併願の具体的な例
たとえば、第一志望がある大学の総合型選抜を受けつつ、同時に別の大学の一般入試も受けるという方法です。これにより、万が一総合型選抜で不合格でも、一般入試で再挑戦することができます。
「どの大学を併願するか迷っている…」そんな方もLINEで無料相談できます!
2.2 併願の種類と特徴
併願をするときには、受験の戦略としてどのタイプの併願を選ぶかが重要です。併願にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリットがあります。今回は代表的な併願の種類についてご紹介します。
併願の種類
総合型選抜(AO入試)と一般入試の併願
この併願方法は、最も多くの受験生が選ぶ方法です。総合型選抜での出願をしつつ、一般入試にも挑戦することができます。
メリット:併願することで、総合型選抜で不合格でも一般入試で再挑戦ができるチャンスが増えます。
注意点:試験日程が重ならないようにスケジュールを調整する必要があります。
総合型選抜と推薦入試の併願
こちらは、総合型選抜と推薦入試を併せて受ける方法です。推薦入試は、学校の推薦を受けて進学するため、学力の基準が総合型選抜よりもやや緩やかであることが多いです。
メリット:総合型選抜の合格のチャンスとともに、推薦入試を通じて早期に合格が決まる可能性があります。
注意点:推薦入試の条件に合った活動実績が必要です。
複数の大学の総合型選抜の併願
複数の大学で総合型選抜を受ける場合もあります。この場合、各大学の選抜基準や求められる条件を事前にしっかり把握し、準備を進めることが大切です。
メリット:受験できる大学が増えることで、合格のチャンスが広がります。
注意点:受験料や提出書類の準備に時間とコストがかかることがあります。
併願を選ぶ際のポイント
スケジュールの調整
複数の大学を受ける場合、試験日程や提出物の期限が重ならないように計画的にスケジュールを組むことが大切です。
志望理由の明確化
併願する大学それぞれに対して、なぜその大学を選んだのかをしっかりと説明できるように準備しておきましょう。大学ごとの志望理由を明確にしておくことで、面接や推薦書作成の際に有利になります。
入試方式の特徴を理解する
各入試方式(総合型選抜、推薦入試、一般入試など)の特徴をしっかり理解し、それぞれの強みを生かした対策を行いましょう。
▶︎3. 総合型選抜における併願の可否

3.1 総合型選抜と専願の関係
総合型選抜を受ける場合、多くの大学では専願という条件を設けていることがあります。専願とは、その大学に合格した場合、他の大学には合格しても入学しないという約束をすることです。では、総合型選抜と専願の関係について、詳しく見ていきましょう。
総合型選抜と専願の基本的な考え方
専願は、総合型選抜の特徴的なルールの一つです。多くの大学がこのルールを採用している理由は、次のような点にあります。
大学側の信頼を得るため
総合型選抜は、学力だけでなく、受験生の意欲や個性を評価するものです。大学は「この学生をぜひ迎えたい」という思いで受け入れを決めます。そのため、専願にすることで、合格した学生が確実に入学してくれることを保証したいと考えているのです。
受験生側の意思確認
大学が専願を求める背景には、受験生の真剣さを確かめるという意図があります。専願を選ぶことで、入学を希望している意志がはっきりと伝わります。
併願可能な大学と専願の違い
一部の大学では、総合型選抜で専願を求めつつも、他の大学の入試を併願できる場合があります。しかし、ほとんどの大学では専願を選ばなければ併願は認められないことが多いです。
併願を許可している場合でも、次のような制限があることがあります。
併願の範囲が限定される
一部の大学では、総合型選抜専願を条件に、他の大学の一般入試や推薦入試に限り併願を認めているケースもあります。
併願を前提にした場合、学費や入学後のサポートが異なる
併願をしている場合、合格した大学に対してどのように対応するか、事前に理解しておく必要があります。
専願と併願のどちらを選ぶか
総合型選抜において専願か併願かを選ぶ際には、次の点を考慮することが大切です。
第一志望の大学に対する熱意
もし第一志望の大学に対する強い熱意がある場合は、専願を選んだ方が有利です。専願を選ぶことで、大学側からの信頼を得やすく、合格のチャンスが広がります。
リスクヘッジをしたい場合
一方、専願に対して不安がある場合や、他の大学も視野に入れておきたい場合は、併願を選ぶことが合理的です。併願をすることで、合格するチャンスを増やし、万が一のための保険をかけられます。
3.2 併願を許可している大学の事例
総合型選抜を受ける際、多くの大学では専願を求められますが、併願を許可している大学も存在します。併願を許可している大学では、受験生に対して柔軟な対応をしているため、複数の大学に挑戦するチャンスを広げることができます。今回は、併願を許可している大学の事例をご紹介します。
併願を許可している大学の特徴
総合型選抜で併願を許可している大学には、いくつかの共通点があります。
選抜方法に柔軟性がある
これらの大学では、総合型選抜において志望理由書や面接を重視しているため、試験の結果だけでなく、受験生の意欲や個性を重視する姿勢を見せています。このような大学では、試験日程が重ならない範囲で、他の大学との併願を許可しています。
他の入試方式と併願可能
一部の大学では、総合型選抜と推薦入試や一般入試との併願を認めています。この場合、学力試験がない総合型選抜を受けつつ、学力試験がある一般入試を受けることができるため、合格のチャンスを増やすことが可能です。
併願を許可している代表的な大学
早稲田大学
早稲田大学の一部学部では、総合型選抜(AO入試)と推薦入試、さらに一般入試を併願することができます。特に、総合型選抜を受けた場合でも、他の学部や一般入試を受けることができるため、受験生にとって柔軟な選択肢を提供しています。
立命館大学
立命館大学では、総合型選抜と一般入試の併願を許可しています。併願することで、万が一総合型選抜に不合格となった場合でも、一般入試に進むことができるため、安心して受験に臨むことができます。
関西大学
関西大学では、総合型選抜(AO入試)と一般入試の併願が可能です。試験日程が異なる場合、同じ年度に異なる学部を併願することもできます。これにより、より多くの選択肢を持ちながら受験に挑むことができます。
併願を許可する大学を選ぶ際のポイント
併願を許可している大学を選ぶ際には、次の点を考慮しましょう。
試験日程の調整
併願をする場合は、各大学の試験日程を事前に確認し、重ならないように調整することが大切です。複数の大学の試験を受ける際、スケジュールが合わないと受験できないことがあるため、早めに確認しておきましょう。
志望理由を明確にする
併願を行う場合、複数の大学に対してなぜその大学を志望するのかを明確にし、それぞれの志望理由書に反映させることが大切です。各大学の特色や教育内容に合った理由を記載することで、面接や選考で強い印象を与えることができます。
総合型選抜の対策法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください!
実際の対策方法やポイントをわかりやすく解説しています。
4. 併願時の注意点と戦略
4.1 スケジュール管理の重要性
総合型選抜や併願を進める中で、スケジュール管理は非常に重要なポイントです。受験生にとって、複数の試験日程や提出物の締め切りを効率よくこなすためには、計画的に行動することが求められます。
なぜスケジュール管理が重要なのか?
受験をする際には、試験日程や提出期限が重なったり、準備に時間がかかりすぎてしまうことがあります。これを避けるためには、早い段階からスケジュールを立て、余裕を持って準備することが成功へのカギになります。
複数の試験日程を重ねないために
総合型選抜や併願では、いくつかの試験を受けることが多いため、試験日程が重ならないように調整することが大切です。具体的には、各大学の試験日程や提出物の締め切りを早めに確認し、どの日にどの試験を受けるのかを決めておきましょう。
試験日程のチェック
受験する大学の情報をしっかりと把握し、重複しないようにスケジュールを調整します。万が一重なった場合は、受験できる大学を一つに絞る必要が出てきます。
提出物の確認
総合型選抜では、志望理由書や自己推薦書、小論文などの提出物があります。これらを準備する時間をしっかり確保し、締め切りに遅れないように注意しましょう。
余裕を持った準備の大切さ
スケジュールに余裕を持って準備することで、試験前に焦ることなく、しっかりと自分の実力を発揮できる状態にしておくことができます。特に、試験の直前に焦って勉強したり、書類作成を急いだりすることは避けたいですよね。
計画的に学習時間を確保
どの科目にどれだけの時間をかけるかを計画し、日々の学習を積み重ねていきましょう。特に総合型選抜では、学力試験だけでなく面接や小論文の準備も必要です。これらを並行して進めるためにも、早い段階で学習計画を立てることが肝心です。
休息時間も確保
受験勉強を続ける中で、適度な休息を取ることも大切です。勉強だけに没頭してしまうと、体調を崩す原因になりますので、休憩時間や睡眠をしっかりと確保し、心身ともにベストな状態で受験に臨みましょう。
4.2 各入試方式の対策方法
総合型選抜にはさまざまな入試方式があり、対策を立てることが成功への近道です。ここでは、総合型選抜(AO入試)、推薦入試、一般入試の対策方法を紹介します。
1. 総合型選抜(AO入試)の対策
志望理由書の作成
志望動機や将来の目標を具体的に書く
自分の経験や活動実績をしっかり伝える
面接準備
自分の強みや意欲を明確に伝える練習
面接官の質問に答えるための事前練習
小論文対策
時間内で論理的に書けるように練習
事前にテーマを予想し、いくつかのトピックについて考える
2. 推薦入試の対策
学校推薦書の提出準備
自分のアピールポイントを明確に伝える
学校の教師とコミュニケーションを取り、推薦をもらう
面接対策
質問内容を予測し、答えを準備しておく
自分の将来の目標や志望理由を整理しておく
3. 一般入試の対策
学力対策
苦手科目を重点的に勉強し、強化する
過去問を繰り返し解き、出題傾向をつかむ
時間管理の練習
実際の試験時間に合わせて模擬試験を実施し、時間配分を確認する
「各入試方式に向けた具体的な対策が知りたい!」そんな方もLINEで無料相談できます!
4.3 志望理由書・自己推薦書の作成ポイント
志望理由書や自己推薦書は、総合型選抜や推薦入試で非常に重要な書類です。これらの書類を通じて、大学に自分の意欲や強みをしっかりと伝えることが求められます。
志望理由書の作成ポイント
大学と学部の選択理由を明確に
なぜその大学・学部を選んだのか、具体的な理由を述べる
学部の特色や学びたいことを中心に説明
自分の目標と大学での学びをつなげる
大学で学ぶことが将来の目標にどうつながるかを示す
将来像を具体的に描き、そのためにどんな学びが必要かを説明
自分の経験を具体的に書く
高校時代の活動や経験(部活動、ボランティアなど)を具体的に紹介
どのように成長したか、どんな能力を身につけたかを強調
自己推薦書の作成ポイント
自分の強みを具体的にアピール
得意なことや他の人と差別化できる点を具体的に述べる
活動実績や成績だけでなく、自分の人物像を伝える
大学側が求める学生像を意識する
大学の選考基準を調べ、それに合わせた内容を盛り込む
志望学部に適した人物像を描くことが大切
▶︎5. 成功するための具体的な対策
5.1 志望理由書の効果的な書き方
志望理由書は、大学に自分の意欲や適性を伝える大切な書類です。効果的に書くためには、大学が求めている人物像に合った内容を盛り込み、論理的に構成することがポイントです。
1. 大学・学部の特色を理解する
大学の理念や学部の特徴をリサーチ
大学の教育方針や特徴的なカリキュラムを確認し、それに自分の志望動機を合わせる
学部で学びたいことを具体的に書く
学部で学びたい内容を挙げ、その理由を自分の興味や経験に基づいて説明
2. 自分の将来像とつなげる
大学で学ぶことが将来の目標にどうつながるかを示す
目指す職業や社会的な貢献を明確にし、大学での学びがその実現にどう寄与するのかを具体的に記述
将来のビジョンを描く
自分のキャリアビジョンを描き、どのように学んで成長したいかを説明
3. 自分の経験や強みを活かす
高校時代の経験や活動を具体的に示す
ボランティア、部活動、インターンシップなど、具体的な実績を挙げて、どのように成長したかを示す
自分の強みを生かせる点をアピール
自分の能力や経験が大学の学びにどのように役立つかを説明
5.2 自己推薦書の作成方法
自己推薦書は、自分の強みや特性をしっかり伝えるための大切な書類です。大学側に自分がどんな人物で、どんな能力を持っているかをアピールする場なので、具体的な事例を盛り込み、説得力を持たせることが重要です。
1. 自分の強みを明確にする
自己分析をしっかり行う
自分の強みや特徴を明確にするために、これまでの経験を振り返る
自分の性格やスキル、能力を具体的にリストアップする
得意分野を強調
学業、部活動、ボランティア、アルバイトなどの実績を挙げて、どんな結果を出したかを示す
2. 実績を具体的に示す
成果や成果物を紹介
自分が関わった活動で得た成果や賞、実績を具体的に記載
例えば、「○○コンテストで最優秀賞を受賞」などの事実を強調する
成長の過程を描く
どのように成長したか、苦労した点や乗り越えた経験を具体的に示す
3. 大学にどのように貢献できるかを考える
自分の経験が大学生活にどう生かせるかを述べる
過去の経験やスキルが大学でどのように活かされるのか、具体的に描写
学部や大学で学びたいことにどう繋がるのかを説明
5.3 小論文対策のポイント
小論文は、総合型選抜や推薦入試でよく求められる試験科目で、自分の考えを論理的にまとめて表現する力が試されます。効果的に対策するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
1. 課題をしっかり理解する
テーマをよく読み解く
出題されたテーマが何を求めているのか、指示をしっかり理解することが最初のステップです。
具体的な問題点や問いに対して、自分の立場を明確にすることが大切です。
2. 論理的な構成を心がける
序論・本論・結論を意識
序論でテーマの問題提起を行い、本論で自分の意見を展開、結論でまとめる構成にします。
本論では、根拠や具体例を挙げて論を進めることが大切です。
3. 時間配分を意識する
制限時間内で完結させる練習
まずは制限時間内で論文を書き終える練習を繰り返すこと。
時間配分を計画的に行い、最後に見直す時間を確保するようにしましょう。
4. 文章表現を工夫する
簡潔で分かりやすい表現を使う
複雑すぎる言い回しや難解な表現は避け、誰が読んでも理解しやすい文章を書くことを心がけましょう。
例え話や具体的なデータを使って、説得力を高めるのも有効です。
「どの大学を併願するか迷っている…」そんな方もLINEで無料相談できます!
▶︎6. まとめ
総合型選抜や併願を成功させるためには、入試ごとの特徴をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、総合型選抜と併願に関する重要なポイントをおさらいし、今後の受験に向けた効果的な戦略をまとめます。
1. 総合型選抜の特徴とメリット
学力試験だけではなく、人物評価や意欲が重視される
早期に合格が決まるため、余裕を持って大学生活に臨むことができる
志望動機や自分の強みをしっかりとアピールすることが重要
2. 併願の活用法
併願することで、受験のチャンスが広がり、万が一のリスクを減らすことができる
試験日程や評価基準を調整し、うまく併願することで、合格の可能性を高められる
志望理由書や面接で、複数の大学への熱意をしっかり伝えることが大切
3. スケジュール管理の重要性
複数の入試を受ける場合、試験日程や提出物の期限を事前に調整し、余裕を持った準備を進める
スケジュール管理をしっかり行い、時間配分を意識しながら学習を進めることが合格へのカギ
4. 書類作成のポイント
志望理由書や自己推薦書は、大学の特徴に合わせてしっかりと自分をアピール
自分の強みや経験を具体的に示し、大学で学びたいこととつなげることが重要
小論文では、論理的な構成と説得力のある表現を意識して書く
▶︎総合型選抜の対策ならEQAOにお任せください!
総合型選抜や併願について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひEQAOのサービスをご利用ください。志望理由書や自己推薦書の書き方、面接対策、小論文対策まで、専門的なアドバイスがもらえます。
EQAO公式LINEでも、あなたの受験に合わせた個別のサポートを受けられます。試験の準備に不安がある方、合格を確実にしたい方、今すぐご相談ください!
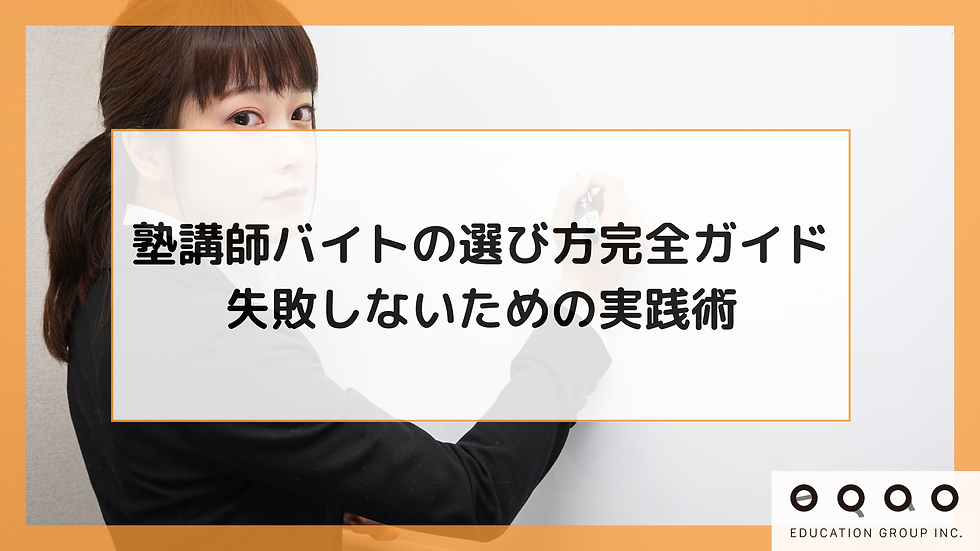


コメント