成蹊大学 国際共創学部のAOマルデス入試対策|新設学部の特徴と合格戦略
- 株式会社EQAO教育グループ

- 2025年8月25日
- 読了時間: 17分

▶︎1. 成蹊大学 国際共創学部のAOマルデス入試とは

1.1 マルデス入試の特徴と目的
成蹊大学のAOマルデス入試は、一般的な学力試験だけでは測りきれない力を評価する特別な入試方式です。名前の由来は 「The Multi Dimensional Entrance Examination for Seikei University」 で、多面的に受験生を評価する仕組みが込められています。
この入試が目指しているのは、単なる学力試験で優秀な人を集めることではありません。将来の目標を描き、それを実現するために主体的に動ける人材を発掘することです。そのため、志望理由書や課題レポート、面接やプレゼンテーションを通じて、自分の経験や考え方をしっかり表現することが求められます。
AOマルデス入試の大きな特徴を整理すると次の通りです。
受験生の個性を重視:学力テストでは表れにくい思考力・表現力・協働力を評価
多様な背景に対応:帰国生、社会人、外国人など幅広い出願枠がある
将来を見据えた審査:これまでの取り組みや今後の挑戦を重視
この仕組みにより、たとえば部活動やボランティアでの経験を通じて学んだこと、英語や探究学習で磨いた力などが大きく評価されます。
一方で、よくある失敗もあります。
①「学力試験がないから簡単」と油断する
② 志望理由が漠然としている
③ 書類や面接で一貫性のない内容を話してしまう
こうした失敗を避けるためには、自己分析を丁寧に行い、自分がこの学部で何を学び、将来どう活かしたいのかを明確にしておくことが欠かせません。
忙しい高校生活の中で自己分析や志望理由の整理を後回しにしてしまうと、本番直前に焦って準備する羽目になります。1日30分でもいいので、自分の経験を書き出す習慣をつけておくと、書類作成や面接での受け答えがスムーズになります。
AOマルデス入試は「自分の物語」を伝える舞台です。準備の早さと深さが、そのまま合格への近道になります。
1.2 国際共創学部の新設背景と狙い
成蹊大学が2026年4月に開設を予定しているのが 国際共創学部 です。この学部が注目されている理由は、大きく分けて2つあります。ひとつは、グローバル化や社会課題の多様化に対応するための新しい教育を提供すること。
もうひとつは、大学としての将来的なブランド強化を狙っている点です。
国際共創学部の新設には、次のような背景があります。
社会の国際化:文化交流、国際協力、サステナビリティなどの分野で活躍できる人材が求められている
持続可能な社会の実現:環境やエネルギー問題など、次世代が解決すべき課題が増えている
大学の経営戦略:新しい学部を作ることで、学生募集の拡大や大学の魅力アップを図る
実際、新設学部は大学にとって“広告塔”の役割も担っています。時代に合ったテーマを掲げることで、社会的な注目を集め、将来的な人気学部に育てていこうという狙いがあるのです。
ただし、受験生にとっては大きなチャンスでもあります。なぜなら、初年度の新設学部では次のような傾向が見られるからです。
実質的な合格者数が多め
募集定員に対して多めに合格を出すことがあり、倍率だけを見て尻込みする必要はありません。
志望理由が通りやすい
カリキュラムが社会課題と直結しているため、自分の関心と学部のテーマが一致すれば高く評価されやすいです。
大学が積極的に採用する段階
新設学部の実績を作るため、幅広い背景を持つ学生を集める姿勢があります。
一方で、気をつけたい点もあります。
「新設だから受かりやすい」と安易に考えるのは危険
志望理由が浅いとすぐに見抜かれる
認可申請中など、制度やカリキュラムが変更される可能性がある
これらを踏まえると、「なぜ国際共創学部なのか」「自分の将来とどう結びつくのか」 を丁寧に語れるかどうかが合否を分けます。
忙しい受験準備の中でも、SDGsや国際協力、文化交流など、自分が一番関心のあるテーマを日常生活の中で掘り下げておくと、自然と説得力のある志望理由に仕上がっていきます。
国際共創学部は、学問と社会を結びつけ、自分の夢を世界規模で形にできる場所です。
1.3 AOマルデス入試で評価されるポイント
AOマルデス入試では、従来の学力試験とは異なり、「人物評価」 が中心となります。つまり、知識の量ではなく「これまでどう行動してきたか」「将来どんな挑戦をしたいのか」が重視されるのです。
評価の柱は大きく分けて次の3つです。
自己分析と将来像
これまでの経験から自分が何を学び、どんな力を伸ばしてきたのか。そして、その延長線上にどんな未来を描いているのか。これが一貫していると高く評価されます。
表現力と論理性
プレゼンテーションや面接では、自分の考えを筋道立てて伝える力が問われます。特に国際共創学部では、多様な背景を持つ人と協働する力が求められるため、分かりやすく相手に伝えるスキルは必須です。
社会課題とのつながり
国際日本学や環境サステナビリティといった専攻は、どちらも現代社会の課題と直結しています。そのため、自分の関心と社会的テーマをどうリンクさせているかがポイントになります。
ただし、準備不足だと次のような失敗をしがちです。
① 志望理由が「有名だから」「就職に有利そうだから」と浅くなる
② 活動報告書に事実を並べただけで、学びや成長を語れていない
③ 面接で緊張して、自分の言葉で語れずに暗記した文章を読み上げてしまう
こうした失敗を避けるには、普段から「なぜその活動を選んだのか」「そこから何を学んだのか」を言葉にする練習が大切です。たとえば、部活や文化祭の経験を友人や家族に説明するだけでも、自分の言葉で表現する力が磨かれていきます。
AOマルデス入試では、「あなたが何をしてきたか」以上に「なぜそれをして、今後どう活かすのか」が評価の核心になります。
\ 成蹊大学 AOマルデス入試で合格を狙うならEQAO! /
志望理由の作成から英語資格・課外活動まで徹底サポート!
新設学部を戦略的に活用し、合格を勝ち取りましょう。
▶︎2. 成蹊大学 国際共創学部のAOマルデス入試の出願条件

2.1 共通要件と受験資格
AOマルデス入試に出願するには、学力試験の成績だけではなく、大学が定める条件を満たす必要があります。成蹊大学では「誰でも自由に出願できる」というわけではなく、志望の強さや将来像の明確さ が共通要件として求められています。
主な共通条件は以下のとおりです。
成蹊大学での学びを強く志望し、合格したら必ず入学する意思を持つこと
将来に向けた目標が明確で、それに向けて努力していること
志望学部の学びが自分の目標達成に直結していること
出願時点で所定の年齢に達していること(18歳以上、社会人枠は21歳以上)
つまり、受験資格は単なる形式的な条件だけではなく、「大学で学ぶ理由が明確かどうか」が審査の前提になっているわけです。
ここでよくある勘違いは次のようなものです。
① 出願条件を「年齢や学歴の条件」だけだと思ってしまう
② 志望理由を「書類上で整えればいい」と軽視してしまう
③ 「合格したら必ず入学」という約束を曖昧に考えてしまう
これらの失敗を防ぐには、出願前に必ずチェックリストを作ると安心です。たとえば:
志望理由は一貫して説明できるか
自分の将来像と学部の学びを関連づけて話せるか
入学後のプランを言葉にできるか
こうした準備をしておくことで、出願要件の「形式」だけでなく「中身」もクリアできます。
日常生活での工夫としては、授業や部活、ボランティアの中で感じたことをノートにまとめておくのがおすすめです。後から見返すことで、自分の成長を具体的に語れる材料になります。
AOマルデス入試の出願資格は“書類上の条件”だけでなく、“本気度”を測るフィルターでもあるのです。
2.2 出願区分(一般・帰国生・社会人・外国人)の違い
AOマルデス入試では、受験生のバックグラウンドに応じて複数の出願区分が設けられています。大きく分けると 一般・帰国生・社会人・外国人 の4つで、それぞれに特徴があります。
まずは全体像を整理してみましょう。
一般受験:高校を卒業した(または卒業見込みの)人が対象
帰国生特別受験:海外で一定期間以上学校教育を受けた経験を持つ人が対象
社会人特別受験:21歳以上で、職業経験を1年以上持つ人が対象
外国人特別受験:日本国籍を持たず、日本での学びを希望する人が対象
これらの区分は単なる「入口の違い」に見えるかもしれませんが、実は大学が求めている学生像を反映した仕組みでもあります。
たとえば、帰国生枠では「異文化での学びや経験をどう活かせるか」が評価されます。社会人枠なら「仕事や社会経験をどう大学での学びにつなげるか」が問われます。外国人枠では「日本社会とのつながりをどう築くか」に焦点が置かれます。
ここで気をつけたいのは、次のような失敗です。
① 自分の経験がどの区分に当てはまるのかを誤解してしまう
② 区分ごとの審査の視点を無視して、一般的な志望理由だけを書いてしまう
③ 「自分は特別枠だから有利」と思い込んで準備を怠る
これを避けるためには、まず募集要項を細かく確認することが第一歩です。そして「なぜ自分がこの区分で出願するのか」を説明できるようにすることが重要です。
日常的な準備としては、自分のバックグラウンドを棚卸ししてみましょう。海外生活で得た文化体験、社会人としての職務経験、日本で学びたい動機などを書き出しておくと、書類や面接で説得力が増します。
AOマルデス入試は区分ごとに“光るポイント”が異なるため、自分の背景をどう強みに変えるかが合格のカギになります。
2.3 出願に必要な書類と準備の流れ
AOマルデス入試では、学力試験よりも提出書類が大きな役割を果たします。書類は「これまで何をしてきたか」「今後どんな未来を描いているか」を示す材料になるため、準備に時間をかける必要があります。
主な提出書類は次の通りです。
志願書(大学所定の様式)
志望理由書
活動報告書
課題レポート
英語外部検定試験の成績証明書
調査書(または卒業証明書・成績証明書)
区分ごとの追加書類(帰国生なら海外在留証明、社会人なら履歴書など)
これらの書類は一見シンプルですが、実際には 自己分析・文章力・一貫性 が問われるため、早めの準備が必須です。
準備の流れを整理するとこうなります。
自己分析からスタート
自分の経験や強みを整理し、学びたいテーマと将来像を明確にする。
志望理由書の下書き作成
「なぜこの学部なのか」「将来どう活かすのか」を軸に文章を組み立てる。
活動報告書と整合性を確認
志望理由で語った内容と、実際の活動実績がつながるように整理する。
課題レポートの仕上げ
指定テーマについて論理的にまとめ、自分の考えをしっかり表現する。
証明書類を早めに依頼
調査書や証明書類は学校や役所を通す必要があるため、直前に依頼すると間に合わない可能性がある。
AOマルデス入試の出願は“提出物勝負”。早めに動き、書類を通じて自分の物語をきちんと伝えることが合格の第一歩です。
【知らなきゃ損】総合型選抜において新設学部は狙い目か?
総合型選抜対策塾EQAOの塾長が語る!
▶ 今すぐ動画をチェック!
▶︎3. 成蹊大学 国際共創学部 AOマルデス入試の選考方法
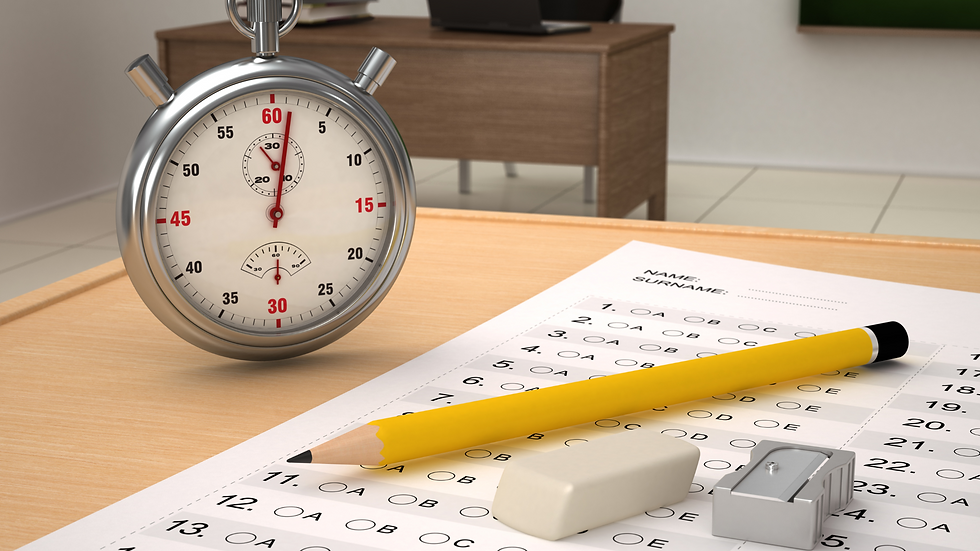
3.1 一次審査(書類審査)の内容と注意点
一次審査は提出書類をもとに評価され、学力試験よりも「人物像」が重視されます。
【審査対象】
志望理由書:学部とのつながり、将来像の明確さ
活動報告書:実績よりも学び・成長をどう語るか
課題レポート:論理性や独自の視点
調査書:基礎学力や努力の継続性
英語外部検定:語学力の証明
【よくある失敗】
志望理由と活動内容が一致していない
知識だけでまとめ、個性が出ない
証明書類の準備を忘れる
【突破のコツ】
書類を一貫したストーリーでつなぐ
自分の言葉で経験を説明する
夏前から計画的に準備する
一次審査は「提出物勝負」。深みのある自己表現が合否を分けます。
3.2 二次審査(プレゼン・面接)の対策ポイント
二次審査では、発表力と対話力が大きな評価対象となります。
【審査内容】
プレゼンテーション:指定テーマを基に意見を発表
質疑応答:論理性・柔軟性をチェック
志望理由面接:学部選択の一貫性と熱意
【よくある失敗】
原稿丸暗記で質問に対応できない
資料やスライドに頼りすぎる
緊張で声が小さく、熱意が伝わらない
【対策のポイント】
家族や友人に3分スピーチを繰り返す
想定質問を10個以上リスト化し練習
姿勢・声・表情も評価対象と意識
二次審査では「完璧さ」よりも「自分の考えを自分の言葉で語れるか」が最大の評価ポイントです。
3.3 よくある失敗例と合格のための工夫
AOマルデス入試では、準備不足や浅い志望理由が落とし穴になりやすいです。
【よくある失敗】
志望理由が「有名だから」「就職に有利そう」で浅い
活動報告が実績の羅列だけで学びが伝わらない
面接で暗記文を読み上げ、自然な表現ができない
【合格のための工夫】
「なぜその学部か」を自己分析で深掘りする
活動経験から得た気づき・変化を言葉にする
キーワードをメモにして、自分の言葉で話す練習をする
【日常でできる準備】
部活やボランティアで感じたことを日記に書く
家族に「今日学んだこと」を説明して表現力を鍛える
ニュースや社会課題を自分の興味と結びつけて考える
合格する人は“経験を物語に変える力”を持っています。小さな工夫の積み重ねが本番で大きな自信になります。
\ 成蹊大学 AOマルデス入試で合格を狙うならEQAO! /
志望理由の作成から英語資格・課外活動まで徹底サポート!
新設学部を戦略的に活用し、合格を勝ち取りましょう。
▶︎4. 新設学部を狙うメリットと注意点
4.1 新設学部は合格のチャンスが広がる理由
新設学部は大学にとって「初年度から学生を集めたい」という事情があり、合格の可能性が高まる傾向があります。
【チャンスが広がる理由】
実質合格者が多い:倍率が高く見えても、多めに合格を出すケースがある
積極的に採用:大学の“広告塔”として多様な学生を集めたい
志望理由が通りやすい:時代性のあるテーマと個人の関心が結びつきやすい
【よくある誤解】
「新設だから簡単に受かる」と思ってしまう
倍率の数字だけを見て判断する
志望理由を浅く書いてしまう
【対策のポイント】
新設学部の教育内容と自分の関心を具体的に結びつける
「なぜこの学部でなければならないか」を明確に語れるようにする
入試要項の変更点や認可状況を常に確認する
新設学部は“戦略的に狙えるチャンス”ですが、強い志望理由が伴わなければ突破は難しいです。
4.2 志望理由が通りやすいケースと落ちやすいケース
新設学部はテーマが社会課題と直結しているため、関心がマッチすれば高評価につながります。ただし、動機が浅いとすぐに見抜かれます。
【通りやすい志望理由】
SDGs・環境問題・国際協力など社会課題と関連づけている
自分の体験(留学・ボランティア・探究学習)と直結している
学びを将来の進路やキャリアにどう活かすかを具体的に描けている
【落ちやすい志望理由】
「倍率が低いから」「新しいから」と安易に選んだ
「国際的に活躍したい」など抽象的で中身がない
学部での学びと自分の将来像が結びついていない
【対策のポイント】
体験と学部のテーマを結びつけ、ストーリーとして語る
一般的な言葉ではなく、自分の言葉で具体的に表現する
将来の目標と学部の学びを一貫させる
志望理由は“熱意”ではなく“具体性”で差がつきます。自分の体験をどう学部に結びつけるかが合否の分かれ目です。
4.3 新設学部ならではの注意点(倍率や認可など)
新設学部はチャンスが広がる一方で、特有のリスクや注意点もあります。数字や制度だけに安心せず、冷静に準備することが大事です。
【注意すべき点】
倍率の見かけと実態の差:募集定員に対して多めに合格者を出すこともあるが、油断は禁物
認可の不確定要素:設置認可の状況次第で内容や募集人員が変更になる可能性がある
情報の少なさ:新設のため卒業生の進路やカリキュラム実績がまだ不透明
【よくある失敗】
「定員が少ないから受けやすい」と思い込み準備不足になる
認可の情報を確認せずに動いてしまう
学部の将来性を考えずに選んでしまう
【対策のポイント】
大学公式HPや最新の入試要項をこまめにチェック
学部のテーマと社会的なニーズを自分の将来にどう活かせるか整理
倍率や合格者数に左右されず、本質的な準備を進める
新設学部は“攻めの選択肢”ですが、情報収集と堅実な準備が成功の鍵になります。
▶︎5. 成蹊大学 国際共創学部ならEQAOへ
5.1 EQAOの特徴と強み
EQAOは総合型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した指導を行い、難関私立大学への高い合格実績を持っています。特に「自己分析から合格まで一貫して支援する」点が強みです。
【EQAOの主な特徴】
総合型選抜に特化:AO入試・推薦入試・カトリック推薦を中心に対策
高い合格率:個別カリキュラムで効率的に成果を出す
ダブル指導体制:大学生講師のリアルな体験+社会人講師の戦略的サポート
全国対応:オンライン・オフライン両方で受講可能
【強みのポイント】
自己分析から志望校選定、書類作成、面接対策まで網羅
英語資格や小論文など“差がつく要素”の個別対策に強い
ボランティア活動やスタディーツアーなど課外活動もサポート
EQAOは「すきを見つけて、すきを伸ばす。」を理念に、生徒の個性を最大限に引き出す総合型選抜専門塾です。
5.2 提供されるサポート内容(自己分析・書類・小論文・面接など)
EQAOでは、出願準備から試験本番までをトータルでサポートしています。単なる勉強指導ではなく、総合型選抜に必要な「自分を表現する力」を育てる指導が中心です。
【サポート内容】
自己分析:強み・弱み、興味関心、将来像を整理
志望校選定:学力・方式を踏まえた現実的なプラン作成
書類作成支援
志望理由書や活動報告書を添削
課題レポートの論理構成を指導
小論文対策:課題図書や時事問題を踏まえた文章表現を強化
面接・プレゼン対策
個人面接やグループディスカッションの練習
論理的な伝え方や姿勢・話し方を指導
【特徴的な取り組み】
英語資格試験の準備もサポート
課外活動プログラムを提案して「経験値」を増やす
短期集中講座やスタディーツアーも活用可能
EQAOの指導は“自分をどう表現するか”に焦点を当てており、AO入試で合格するための力を着実に伸ばせます。
5.3 成蹊大学 国際共創学部志望者への活用メリット
国際共創学部のAOマルデス入試は、志望理由や自己表現力が合否を大きく左右します。EQAOのサポートは、この入試に直結する力を伸ばすのに最適です。
【活用メリット】
志望理由の強化
SDGsや国際協力など社会課題を踏まえた具体的な志望理由を作れる
自己分析を通じて「なぜ成蹊大学なのか」を明確化できる
書類の完成度向上
志望理由書や課題レポートを添削し、一貫性あるストーリーに仕上げられる
面接・プレゼン対策
実際の質疑応答を想定した練習で、自信を持って自分の意見を伝えられる
国際系入試に強い指導実績
英語資格や海外経験をどうアピールするかまで細かくサポート
【特に有効な点】
新設学部特有の「志望理由の通りやすさ」を最大限に活かせる
学部テーマと自己経験を結びつける表現を習得できる
EQAOを活用すれば、国際共創学部で求められる“社会課題に取り組む意欲”を、確実に伝えられる準備が整います。
\ 成蹊大学 AOマルデス入試で合格を狙うならEQAO! /
志望理由の作成から英語資格・課外活動まで徹底サポート!
新設学部を戦略的に活用し、合格を勝ち取りましょう。
▶︎6. まとめ
本記事では、成蹊大学 国際共創学部(新設学部)の特徴と、総合型選抜(AOマルデス入試)対策における戦略を整理しました。新設学部ならではの合格戦略とEQAO活用のポイントを押さえることが重要です。
【要点まとめ】
新設学部は狙い目
実質合格者が多く、倍率に惑わされず戦略的に挑戦可能
大学側が初年度から実績を作りたいため、合格者を多めに設定
志望理由の明確化が必須
社会課題や学部テーマと自分の関心を結びつけることが合格の鍵
EQAOのサポート活用
自己分析・書類添削・面接対策・英語資格対策など一貫サポート
国際系・新設学部志望者向けに特化した指導実績あり
戦略的な併願・準備が有効
募集人員や入試スケジュールを把握し、計画的に出願・準備
ポイントは「学部の特徴を理解し、自分の強みと結びつけた準備」をすること。
▶︎新設学部対策もEQAOが徹底サポート
国際共創学部のような新設学部は、的確な志望理由と表現力が合否を左右します。EQAOなら、出願準備から面接・プレゼン練習までフルサポートが受けられます。
まずはEQAO公式ページをご覧ください。



コメント